正直、タイトルに釣られてしまった感は否めない。アングラ好き、馳星周大好き、代紋Take2読者であるおいらにとっては、内容不足。ん?いや、むしろマンガ・小説通りなので、良かったのか?マンガ、小説で語られていないのは生い立ちや、戦後の混乱期からの推移(この辺りはコンビニで売られているヤクザマンガにはよく語られているが)。ちょっとガッカリ本。それでも今日行った本屋では新書ランキング1位。世の中難しい。
SIerで昔かじったオッサン技術者の日々是雑感
 F1 戦略の方程式 世界を制したブリヂストンのF1タイヤ (角川oneテーマ21)
F1 戦略の方程式 世界を制したブリヂストンのF1タイヤ (角川oneテーマ21)
ブリジストンでF1のタイヤ開発に携わり、良くレース前にもインタビューにも答えていた浜島さんの著書。可夢偉が、右京に!でF1奥深さに魅せられていたので即購入。タイヤの使い方に関しては、可夢偉が、右京に!でも熱の入れ方をはじめかなり詳しく書かれていたけれど、F1をタイヤから切る本だけに、情報量は膨大。開発を巡る日本とのやり取り、物流、ミシュランとのタイヤ戦争、そしてレーサーとのコミュニケーション。何気なくテレビだけ見ていると全く実態はつかめないけれども、これ1冊を読むだけでもレースの面白さが伝わるでしょう。
F1ファンにはお勧めの一冊。
 官僚の責任 (PHP新書)
官僚の責任 (PHP新書)。古賀茂明の事を最初に知ったのは、田原総一郎のブログか対談がきっかけだったろうか。
その後、週刊誌でも名前は見ていたのでちょっと気になった。書籍を手に取った時は仙石官房長官から恫喝を受けた一部始終が気になった。ので、買ったのだと思う。官僚本は、以前「国家の命運」を読んだが、外務省で無く経済産業省とい事もあってレジに運んだと思う。
書籍全般で書かれている官僚像・仕事は、以下。
①作文
②先輩・後輩天下り至上主義
③縦割り
私は祖父が官僚だったけれども、祖父が過ごした定年以降の動きと直近の官僚の動きはずいぶんと違って見える。それこそ戦後の官僚とだいぶ違うのだろう。
それにしても官僚というと、ひどく縦割でひどい仕事をしている印象を持たれがちだし、その一端は克明に描かれ、糾弾されている。確かにその通りなのだけれども、一方で自分や近い会社を振り返ると非常に似ている印象を受ける。部署の壁は厚く、国策よりも部策。作為的にそうしている訳で無くとも、自然とそういう空気があるという点で考えされられた。
ちなみに、著者のとらえる官僚像と、別途レビューは書くが、ケビン・メアの語る官僚像は非常に似ている点は興味深い。
書籍としては及第点。。。

ずいぶん前から書店に並んでいるのは知ってたが、どうにもサッカーとしてのノンフィクションじゃない気がしたり、妙にまとまったタイトルだったので、手が伸びず。サッカー選手のノンフィクションは大半買うので非常に珍しいパターン。ただ、新聞広告で50万部突破と聞いて決心しました。買うと。
本から伝わるのは、ひとつひとつの心を整える方法論ではなく、長谷部の真面目さ。長谷部誠という著名でなければベストセラーにはなっていないだろうが、現役の日本代表選手が、普段感じていること、意識していることが、真面目にひとつずつ整理されていて、それがサッカー選手長谷部のピッチ外での様子や人間模様を描写していると思う。
そして、これだけ表現力のあるスポーツ選手が果たして何人いるのだろうと感じさせられるか。年下とはともても思えない文章力。様々な書籍からの引用。(いくら本を読んでもしっかりと読まないと引用できるほどエピソードを消化できない!!そして、オレは引用できるほど覚えてない!!から余計に驚く)
また、これだけピッチ外の事が書かれているサッカーの本は珍しい。茶髪にした時のエピソードは浦和レッズの内情を表しているようにも聞こえる。Mr.Childrenのベスト15は思わずすぐにiTunesでプレイリストにした。南アフリカワールドカップのエピソードは相変わらず選手によって違うのが面白い。
書くに足りないエピソードは多いが、誠実であること。真摯であること。準備をすること。それが心を整える事だろう。すぐ実践したい。
超訳マキャベリの言葉。忘れてしまったが某かの本を読んでいたときにやけに哲学者や高校の授業で聞いたような名前が多かったので、という事もあって興味があったんだと思う。新書なので読みやすいし購入。
リーダーシップについて書かれている本はここのところ購入する本に多い共通したテーマだけれども、その手の本は綺麗に書かれていることが多い。リーダーたるもの人格者でもあるべきと言う訳か。それとも汚い部分は品位も疑われるからか。
ただこの本は比較的生生しい手法も書かれている。そういう意味でマキャベリに関する興味も膨らむ。
スタッフを惑わせない為には、新戦略の「さわり」を訓練させ、少しだけ慣れさせておけばいい。これによって、よい緊張感を持って新たな仕事に挑むことができる。
普通は常に刺激を与えて緊張感を持たせるとかって言うよね。「惑わせないために」「少しだけ**させておけば良い」という生生しい表現が新鮮w。
約束や契約など気にかけず、人を裏切って混乱させたリーダーが、真面目にやってきた人間や組織を圧倒し、大きな仕事を成功させるのは珍しくない。
これはスティーブ・ジョブズそのもののイメージだね。アップル追放前を非常に思い出させる。
組織が秩序を保ち、全員が利益を享受するには清貧であるべき。
かと思えば、きれいな話も出てくる。
組織論を語るにはドラッカーから教えられる部分もあるが、500年以上前のマキャベリが教えてくれる部分も数知れず。そして人の本質を上手く表現しているようにも感じる。マキャベリの一面を軽く知るには良い本。もう何冊かマキャベリを読ませたいと思わせてくれた時点で良著。
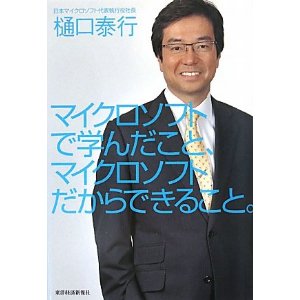 マイクロソフトで学んだこと、マイクロソフトだからできること。
マイクロソフトで学んだこと、マイクロソフトだからできること。
本屋でたまたま目に留まるも、一度は見送り。でも、別の日に行ったときに目に留まり、購入。HPの社長がダイエーの社長になると聞いて、びっくりした記憶があり名前は以前から知っていた。ただし、キャラクターは全く知らず。
本が気になったのも、マイクロソフトの仕事の仕方や考え方が書かれているのが一目取れて分かったから。そういう意味で期待通りの本。
経営陣が細かな数字から各国の状況を詳細に把握しているというのはビックリさせられるも、ソフトバンクでは、役員・上司が現場の詳細を話すことができなければ仕事を役員・上司の意味が無いと切り捨てられる話とも相通づる。
アメリカの経営陣から樋口さんに突きつけられた30以上ある行動指針には優先順位が付けられるものが無く、全ての優先度が高いという話は圧巻。サーベイの徹底・公開も圧巻。これはうちの会社でも仕組み的にはできない話では無い。(ただ、嫌がる人が多いだけ)。全社員を一同に介して年一回行われるイベント。これはうちの会社でもできるだろうが、愛社心があってこそか・・・。XXミーティングの類は多分どこの会社でもやられているだろう。
ただ、全般を通して、果たしてこれほど熱く語れる経営者はどのくらいいるのだろうか。
数日前に部長と話した際も思ったが、熱さが大事だと思う今日この頃。
マイクロソフトも知れますが、熱さを感じたい時に読みたい一冊。
 サムスンの決定はなぜ世界一速いのか (角川oneテーマ21)
サムスンの決定はなぜ世界一速いのか (角川oneテーマ21)
振り返るとここのところ、企業のノウハウ本?が多いですが、これまたタイトルに釣られて買ってみた本。
サムスンの売り上げが日本の大手家電メーカの合算よりも遥かに高いのは新聞で語られている事もありちょっと気になっていたが、一方で、品質が悪かったイメージも残っていた。
が、過剰品質、という言葉に表されるユーザには判別不可能な品質がそのすべてを表している。また、中島聡さんが言う、カタログ作りの日本の家電メーカー、ものを作るユーザを見た製品をおもてなしの心で作らなければいけないという、同じ意見が、サムスンでの仕事を通じて出てきている点は面白い。
また、辻野さんが言う、ソニーの遺伝子ならぬ、松下幸之助さんの遺伝子がサムスンにあるのでは、という考察も興味深い。
優秀な会長の英断によるIMF危機の前に舵を切っていたこと、サムスンに落ちたので国家公務員になると言われるほど集まる優秀な頭脳、海外では徹底的に現地に溶け込ませその土地のディープスマートを獲得させる戦略、大リストラで排除した官僚的な文化、いずれもなるほどと思わされます。
一線で働いてきた方々が語る言葉には、多くの共通点を感じる今日この頃。
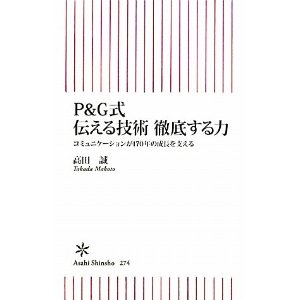 P&G式伝える技術 徹底する力―コミュニケーションが170年の成長を支える (朝日新書)
P&G式伝える技術 徹底する力―コミュニケーションが170年の成長を支える (朝日新書)
P&Gという会社の特徴は全く知らなかったけれども、何かとコミュニケーションがうまく言ってない時だったので購入。
色々なテクニックが紹介されていると共に、人を育てる環境、どのような事がP&Gで求められ徹底されているかという点が強調されており、この点がまさにタイトルにある徹底する力の表れと感じる。
技術面について書かれている本は良くありますが、徹底する点を書かれている本は少ないので良かったです。
また、P&Gそのものがグローバル展開で成功している点の紹介も興味深い。日本人がグローバルに活躍するためには、、、自分だけで考えず世界の知恵を活用すること、自ら情報提供・自己の価値を語り人脈を得ること、知識は作り残していくこと、一つの案件を終えたときに成長を語ること、などなど。また、消費者も世界によって求めるものが異なるので、画一的な展開は絶対にしないこと、など、狭い世界で仕事をしている自分に刺激となる内容が多くあり良かった。
新書というと、面白い内容もありつつ、一冊を通じたメッセージやまとまりが欠けるものも多いですが、珍しく、最初から最後まで一つのテーマに則り書かれた良くまとまった本でした。
良かったトピックス。(3つにまとまってない・・・)
3つにまとめる力
正しいことをする力
お金や資産が、ブランドのすべてが無くなってしまったとしても、社員さえいれば10年で元に戻せる
DemandとCare
(海外と仕事をする際に限らず)「あっち」「こっち」という言葉は厳禁)
自分の価値を語ること
プレミアムビジネスモデル、意識的に世界に目を向ける
etc・・・
前回の更新が開いてしまいましたが、読むのが止まったのではなく、書く時間が確保できなかったためm(–)m。また、こつこつと更新していきたいと思います。と、いうことで、1.5ヶ月ぶりの一冊はこちらから。
買ってから2ヶ月くらい寝かせてしまっていたのだが、タイトルが気になり購入。仕事的には投資銀行なんぞ無縁なんだが。。。
1980年代までの投資銀行と、現在の投資銀行は違う!という事が書かれており、そうなんだ、と思わされる。リーマンショックを契機として出版される本を見る限り、銀行の強欲っぷりは眼に余るところはあるけれども、その契機はゴールドマン・サックスをゴールドマン・サックスたら占めていた、創業家からの流れが途切れた事にある、との記述を読むと、ソニーを思い起こさせる。
また投資銀行家だった著者が、強欲主義な金融に嫌気もさし、本来の実業を重視するよう投資家になっていった事が読み取るに、学生時代にどうしても金融が好きになれなかった自分の姿も思い起こされた。
デトロイトの衰退からの復興も非常に考えされられるテーマだった。
誠実であることの重要性、実業の重要性を、ゴールドマン・サックスと名のつく本が語っている点に、励まされる1冊でした。
F1好き、といってもミーハー感は否めないが、たまらない一冊。思い返せば初めて見たレースが、鈴木亜久里の3位入賞。当時は小学生だったが、セナ・プロストがスタート直後の1コーナーでクラッシュしたり、日本人が活躍する姿は印象的だった。その後はしばらく見ていたんだが、セナの事故死と共に、疎遠に。ただ、佐藤琢磨がF1に来たことから再び見始める。今は可夢偉を見ているだけでF1を見ているわけではないかもしれないが楽しい。
この本は何よりマニアック。書店で平積みされていたので気づいて購入したものの、第1章のオーバーテイクは良いとして、第2章でタイヤの使い方を延々と語っている。レースを見ているとよく聞く言葉だったけれども、初めて、どういうことか分かった。深すぎる。マニアック。
右京のインタビュー形式という点も、良かったんでしょう。
グランツーリスモを通じて車の知識はかなり身についたとの自負があったけれども、やはり浅いですね。とともに、普段は語られることの無い、ナンバー程度の文字数では語れない、深い話があり、F1というスポーツの奥の深さを教えてくれる一冊。
面白かった。
PS:そういえば、中学生のころに、F1裏話なる文庫本を読んだ事を思い出した。その本は多数のドライバーの独特の習慣や、エピソードを書いていたけど、やっぱりひとりに深く斬り込むと印象に残る。その文庫本のエピソードは今となっては、ひとつも覚えていないし(苦笑
PS2:出版社が、東邦出版という会社で、マニアックなスポーツ本も多数出している会社だからこその一冊なのだなと改めて実感。今後、この会社の名前を覚えておこう。。。